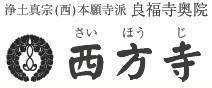平和への願い

- ホーム
- 平和への願い
この一瞬の平和がいつ、崩れていくかはわからない社会であります。
いつまでもこのような平和な社会が続いてほしいと願っていますが、不安定な現代社会です。
辛い悲しかった過去を今ひとたび見つめ、明日に生きる希望を持ってほしい。
いま ここに
自分の番を生きている
それがあなたの命です
それが 私の命です。
他界した先代住職の父・西本 諦了は第2次世界大戦後、抑留者としてウクライナの戦後復興に関わっていました。過酷な抑留生活の中、父は現地住民の温かさに触れていました。
「遠い国であって遠い国ではない。父が知ったら悲しむだろう」。父が抑留中に携えていた輪袈裟を手に、日々平和を願います。

厚生労働省の推計によると、日本兵ら約57万5000人が旧ソ連軍によって抑留され、うち約5万5000人が死亡したとされています。
2011年に94歳で亡くなった父、諦了(たいりょう)は軍隊に召集され、中国東北部(旧満州)で1945年8月の終戦を迎えました。その直後、旧ソ連領に強制連行され、シベリアやウクライナで抑留されました。
3年に及ぶ抑留体験は手記「シベリア・ウクライナ抑留記 命めぐまれ、今を生きる」に残し、強制労働については「言葉では言い表しがたく、つらく、残酷なものだった」とつづっています。

シベリアのインクール収容所では鉱石採掘に従事。氷点下30度にもなる現地で、鉱石をトロッコに積み込む作業を命じられ、「飢餓、極寒、重労働の三重苦」で多くの仲間が命を落としました。
僧侶として「せめてもの供養に」と、毎日のように読経したといいます。その時はベルト裏に縫い付けて隠し持っていた輪袈裟を首に掛けていました。命を大事にしてほしいと願った祖母が、出征前に父のベルトに縫ったのでしょう。
極寒の地では埋葬する穴を掘ることもままならず、砕け散った凍土のかけらをかき集め、遺体にかぶせると『どんなにか、みんなと一緒に日本へ帰りたかっただろうにな』と戦友らを送りました。


46年8月にはウクライナ南部・ザポリージャの収容所に移されました。ウクライナには約5000人が送られ、寒波や栄養失調で約250人が亡くなったといいます。吐く息が凍りつくような厳寒。わずかな食事に争いも絶えませんでした。
大戦で大きな被害を受けたウクライナで、物資の運搬や鉄道建設などに駆り出されました。48年、ようやくかなった日本への帰国時、復興の進んだ街への複雑な思いをこう記していました。「2年前にザパロージェ(ザポリージャ)駅に着いた時とは違って、今は見違えるようにこの町は復興していた/この町が復興できたのもすべて/血の 滲むような過酷な強制労働によるものであることを断言する」
大半は悲惨な抑留生活でしたが、ウクライナ人の温かさにも触れたといいます。建設中のビルで、熱したコールタールを浴びて大やけどを負い、1か月の入院を余儀なくされましたが、医師や看護師の懸命な治療で一命を取り留めました。彼らは「元気になって日本に帰りなさい」と父を勇気づけたといいます。父はウクライナの医師や看護師に命を助けられたことを感謝し、その温かい国民性に励まされていました。


帰国後、父は「生き残った者の務めとして、生ある限り語り継いでいかなければいけない」と、法事など機会を得るたびに自らの体験を語りました。
父の平和や反戦への思いを受け継ぎ、ウクライナに早く平和が訪れることを願います。これまでに支援募金の活動を行い、5月には寺で父の体験やウクライナについて話す講演会も開催。香芝市内であった戦争展では輪袈裟と手紙を展示しました。
戦後のウクライナの礎には抑留者の犠牲や働きもありました。日常生活や都市が破壊されていくことに悲しみ、怒りを感じます。平和を願い、父の思いを語っていきたいと誓います。
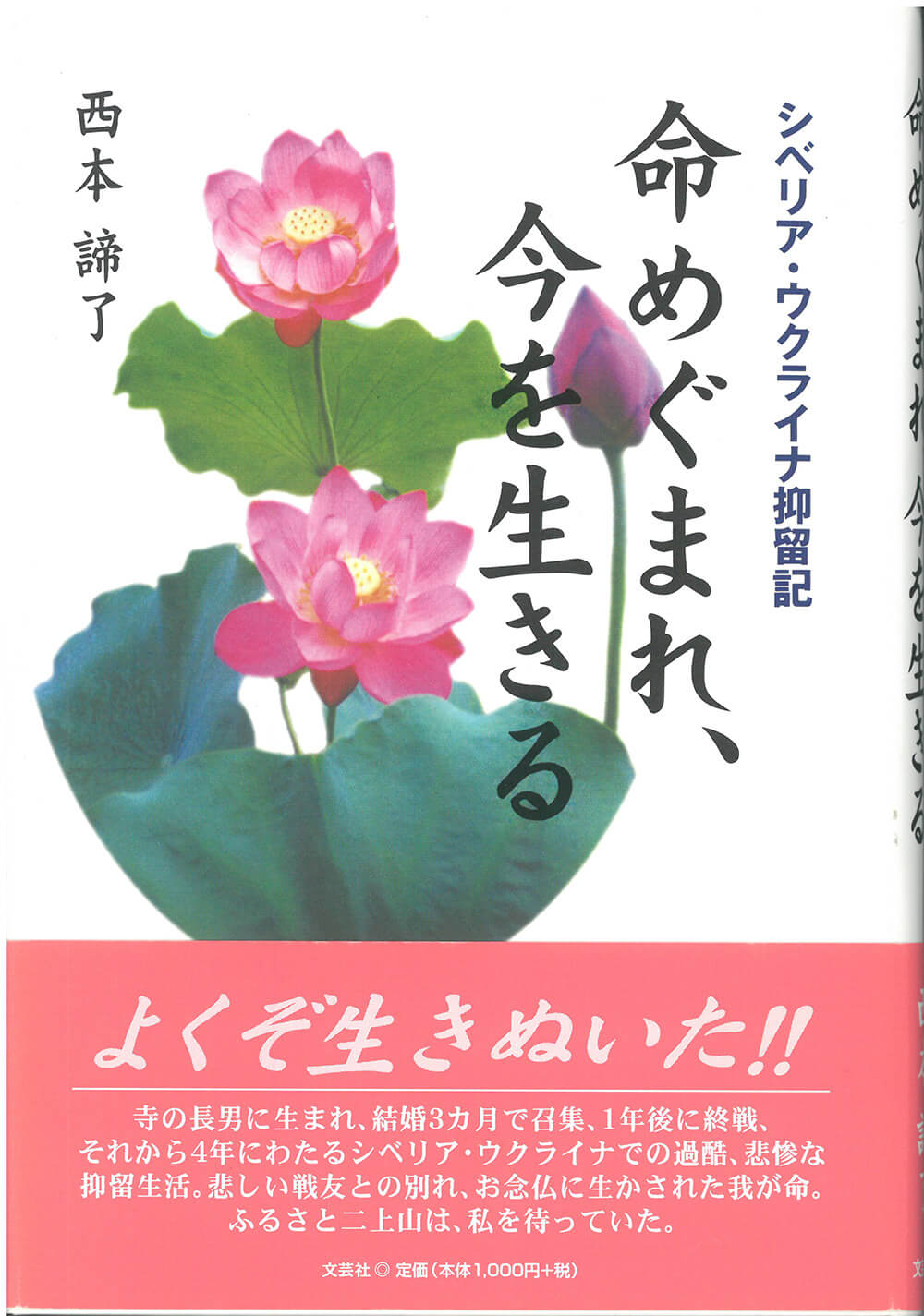
西本 諦了の手記「シベリア・ウクライナ抑留記 命めぐまれ、今を生きる」が文芸社より出版いたしました。是非ご覧ください。